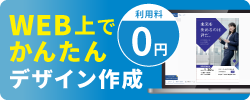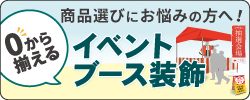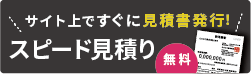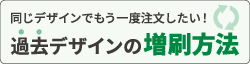展示会で耳にしやすい「小間」の意味を解説!ブースの設置例もわかる

展示会のブースを作る際、小間という単語を耳にして、どんな意味だろうと疑問に思ったことはありませんか。
今回のコラムでは「小間」という意味をはじめ、展示会での小間についてのサイズや施工時にかかる費用、装飾の種類などを解説します。
実際のブースの設置例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
「小間」という言葉の意味
小間という言葉には、次のような意味があります。
- 小さい部屋
- 四畳半以下の狭い茶室
- 少しの間、少しの時間
- 出展者・出展企業に貸し出すために仕切られた展示スペース
1の「小さい部屋」は、家屋の部屋の大きさを表すのに使われます。
2の「四畳半以下の狭い茶室」は、茶道の用語です。
3の「少しの間」は、時間を表す用語として使用されます。
4の「展示スペース」は、展示会や見本市などで使われ、ブースと呼ばれることも多いものです。
今回のコラムでは、4の「展示スペース」という意味で使われる小間について解説していきます。

小間のサイズについて
出展者は展示会主催者から小間を借り、来場者に新製品やサービスのアピールを行います。
1小間のサイズには、特に決まりがありません。会場の大きさやイベントの趣旨によって異なるため、注意してください。
一般的な1小間のサイズは、「3m×3m」の区画スペースが多いです。ほかにも「2m×2m」や「2.7m×6m」などがあるため、事前に確認しましょう。
展示スペースは、基本的に1小間から借りられます。ブースを大きくしたいときは、複数の小間を借りてスペースを増やしていく仕組みです。2小間は「3m×6m」、3小間は「3m×9m」、4小間は「6m×6m」というように面積を増やすことができます。
展示スペースの目安として、小規模(1〜3小間)・中規模(4〜9小間)・大規模(10小間以上)とイメージしておくとよいでしょう。
小間数は展示物に合った、大きすぎず小さすぎないような、ちょうどいい広さを確保することが大切です。
小間の参考費用
1小間あたり、20万円〜60万円が目安です。なお、展示会の規模や人気度によって、かなり幅があります。ブースの施工費やデザイン・装飾費、運送費などを考えると、全体的な費用はさらに上がるでしょう。
また、来場者の目や足が止まりやすい、入り口近くや通路沿い、2面が開放される角小間などの場所は当然人気があります。そのため、抽選が行われたり、追加料金がかかったりすることがあるので注意しましょう。
小間装飾の種類
展示会の小間を構成するブースは、システムパネル、木工、アルミで装飾することが多いです。各装飾について、簡単に解説します。
システムパネルブース

システムパネルブースは、展示会用の仕切りパネルを用いて施工するブースのことです。
パネルやパーツを組み合わせて作り上げるのが基本のため、施工時間が短く再利用もしやすいメリットがあります。デメリットとしては、デザインがワンパターンになりがちになることです。小間に個性を出したい場合は、ほかの装飾も検討してみてください。
木工ブース

木工ブースは、ベニヤ板などを加工して施工するブースのことです。
大工職人の手で加工されることが多く、形状の自由度が高いというメリットがあります。ただし、施工期間が長めであり、コストも高くなる傾向があることは覚えておきましょう。
アルミトラスブース

アルミトラスブースは、連続した三角の骨組みで構成されるフレーム(トラス)を使ったブースのことです。
野外イベントなどでよく見られ、軽量かつ頑丈であることから、高さや存在感を出すのに適しています。なお、施工や撤去に時間がかかるというデメリットがあるため、注意してください。
まとめ
今回のコラムは、「小間」という意味をはじめ、展示会で耳にしやすい小間についてのサイズや、施工時にかかる費用、装飾の種類などをお伝えしました。
実際のブースの設置例も紹介しましたので、イメージも湧いたのではないでしょうか。
展示会やイベントに出展するときなど、小間を設置する際はぜひコラムをお役立てください。
展示会キングでは、展示会やイベントブースに使える販促グッズを多数取り揃えていますので、ぜひチェックしてみてください。